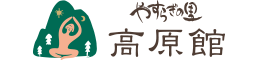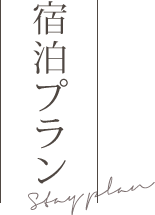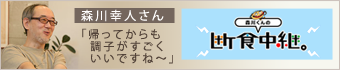こんにちは、こはりです。
食事療法の代名詞的存在である玄米。
マズイという先入観も、どの食品に比してもずば抜けたものがあります。
「自分は実践したいんだけど家族が反対して」なんて言葉をよく聞きます。
たしかに病気治療を念頭に置いた場合、厳格な玄米菜食の効果は、悪食癖極まればこそ絶大なものがあるでしょう。
一方で、生理がこなくなった、ますます症状が悪化した、どんどん痩せていく、などの不安要素もよく聞かれます。
それを治るための反応(瞑眩反応)とみるか、身体の拒絶反応とみるかは専門家の診断力にかかっているといえますが、厳格な食事療法は期間限定で行うべきと個人的には考えています。
食事療法といえども体質、その時の体調に合わせて臨機応変に変化していくものと思うからです。
そして食事療法一辺倒に偏重することにも懸念を表します。
食事とともに睡眠、運動、呼吸はエネルギー代謝の観点からも不可分です。
どんなに良い食物であっても受け手つまり内蔵機能が健全でなければ全く意味がありません。
だからこそ総合的な視点は欠かせないのです。
食事療法も極まれば、修行僧のように眉間にしわを寄せて苦虫を噛み潰すような表情で玄米を何百回とかむようになります。
病気克服のための通過儀礼として、心機一転、形勢大逆転のショック療法としての「行」としての意味合いを持たせるのであれば、それもまた効果ありと言わざるを得ませんが、そこに本人の意志が伴わなかったり、中途でくじけている場合には精神衛生上良くないのはあきらかなことです。
それではどのような食事が理想的であるか。
それは個別の問題なので、短絡的に断言できません。
ただ、ヨガでは同じポーズを続けるとそれ自体が歪みを生むので、いろいろなポーズ、つまりバリエーション豊かな刺激をタイミングよく与えていくことを良しとしています。
食べものも全く同じと考えます。
玄米が良いからといって、それを金科玉条のようにして食べ続けても、そこに信仰にも似た強い信念がある場合は心理的作用を否定できませんが、体はゆがみ、ある部分は鈍化していくのが、身体の法則といえるでしょう。
僕自身は基本的に玄米食肯定派ですが、一週間のうち4~5日にとどめ、そのほかの日は分つき米や雑穀をおりまぜ変化を楽しんでいます。
菜食に関してもほぼ実践していますが、一番大切なことは季節の旬を頂くことと、地域性を重視することだと考えています。
これを「身土不二」と食養の世界では呼んでいますが、身体と風土は切り離せないと考えるのです。
そこには食物をモノや栄養素としてだけ見るのではなく、見えない力、つまり気やエネルギーといった有機的、相互補完的な生命力を認める観点があります。
ただこれも厳密に考えると東京出身の僕がアラスカに移住した場合、アザラシを常食すべしとなりますので熟慮が必要になります。
大まかにいって日本人として、和食が大前提になるでしょう。
その上で、その土地の風習や伝統文化をも楽しむ心の余裕を「身土不二」に見出すのです。
そこには「私は菜食なので」と宴席で頑なに固辞する方々の厳格さはありませんが、自分のことよりもその場を重んじる「和をもって貴しとなす」日本人的な人生の楽しみ方を知る人間であることをあらわしています。
なによりそこには「感謝の心」があると思うのです。
人間はモノとしての体だけでできている存在ではありません。
東洋思想では「身心一如」といいますが、心と体が調和して存在しているとみるのです。
しかも心と体では、心の力の方が強い、7対3くらいに考えてもいいのではないかと思っています。
なぜなら人間はそのほかの生物と明らかに違うことは思考することにあるからです。
そのために高度な文明を築き今日の繁栄があります。
これはまさに人間の心の力、いわば念の威力の為せる業です。
「こうなりたい」という意志は、現実化する力があるようです。
とはいえ「健康になりたい」という強い願いには、逆説的に「私は今病んでいる、弱い存在である」という潜在意識の刷り込みでもあるのです。
ですから「健康になりたい」「病気を治したい」と強く願うほどに、病気である自分を誇張し、場合によっては自分を受け入れられなかったり自分の病気を自分とは全く隔たれた別のもの、つまり敵とみなして駆逐する対象としか見られなくなります。
これでは手術をして切り取る、薬で叩くにとどまり、病気の治癒が生活習慣の改善、つまり生き方にかかっているという人間存在の根源的なところまで思いが及ばなくなる恐れがあります。
ですから「今日も元気に生かせていただきました」の感謝の一念こそが、健康の大原則であると思っています。
僕が常々「治療法が治すのではない自分で治すのだ」と言ってきたのは、他者に頼る依存心こそが潜在意識下における病気の原因ではないかと気付いたからです。
「責任主体は自分」というのは、人間の心の力をどこまでも信頼し、肯定的な結果を引き寄せるのだという希望に根ざしています。
「自業自得」という言葉は、「罰が当たる」ような否定的なイメージがまとわりつきますが、良きにつけ悪しきにつけ、自分で作った原因は相応の結果を引き起こすという自然法則だと思います。
だからこそ、日々営む生活こそが、この一瞬、一瞬の「心持ち」「身持ち」こそが大切なのではないでしょうか。
究極的に言ってしまえば、肉食であれ、白米食であれ、そこに感謝の気持ちがあれば良いという事になります。
感謝して病気になれば、その病気にだって感謝できるというものでしょう。
誰しも遅かれ早かれ必ずお迎えがきます。
「そのとき笑顔でお迎えに応えられるか」そこにすべてが集約されているといっても過言ではないと思うのです。