クリックできる目次
50代から考える認知症予防
「最近、親の物忘れが増えてきて心配になった」
「介護で一番大変だったのは、実は認知症だった」
「自分も将来、子どもに迷惑をかけたくない…」
こんなお話を耳にすることが増えてきました。
50代になると、親の介護が始まったり、
老後のことを少しずつ意識するようになりますよね。
今回は「自分らしく年を重ねるために、今できること」として、
認知症予防についてお話ししたいと思います。
1. 日本の現実:4人に1人が認知症に
現在、65歳以上の高齢者のうち、およそ15%、つまり7人に1人が認知症と言われています。
そして2040年には、その割合が23〜25%、4人に1人になると予測されています。
認知症になると、自分がつらいだけでなく、家族や周囲にも大きな負担がかかります。
とくに精神的な負担は大きく、介護する人が疲れきってしまうことも少なくありません。
だからこそ、「できることがあるうちに」「まだ元気なうちに」
予防に向けて少しずつ意識を向けていくことが大切です。
2. 軽度認知障害(MCI)で気づく・止めるがカギ
認知症の手前の状態に「軽度認知障害(MCI)」があります。
これは、もの忘れが増えてきたけれど、日常生活には支障がない状態。
このMCIの段階で対策を始めれば、3〜4割の人が元の状態に戻れるとも言われています。
「なんだか最近、ぼーっとする時間が増えたな」
「会話するのがおっくうになってきたかも…」
そんな小さな変化も、体と心のサインかもしれません。
無理せず、でも放っておかずに、「できることから始めてみよう」と気づくことが第一歩です。
3. 認知症予防に最も効果的なこととは?
認知症予防は、難しいことをしなくても大丈夫。
日々の生活の中に、「脳を優しく元気にする習慣」を取り入れていくことが何より効果的です。
【交流】
誰かと話すこと、笑うことは、脳の最高のトレーニング。
サークル活動や友人とのお茶の時間、家族との会話も、立派な予防です。
【運動】
ウォーキングやラジオ体操などの軽い運動は、記憶を司る“海馬”を元気にしてくれます。
できれば週に3回、30分ほどを目安に。
【食事】
魚や野菜を中心とした和食がおすすめ。
よく噛んで、ゆっくり食べることで満足感も増え、消化にも優しく、脳にも◎。
【睡眠】
寝ている間に脳はお掃除され、疲れやストレスをリセットします。
夜ふかしは避け、できるだけ同じ時間に寝起きするリズムを整えてみましょう。
【知的刺激】
本を読む、新しい趣味に挑戦する、手書きの日記をつけるなど、脳を「少し使う」ことが大事です。
【心の安定】
呼吸法や瞑想は、脳内のセロトニン(幸福ホルモン)を増やす効果があり、感情の安定にもつながります。
やすらぎの里では、自然の中で体を動かし、
静かに呼吸を整え、やさしい食事を味わう体験を通して、
「心と体を整える習慣」作りを提案しています。
4. 「いつか」じゃなくて「今日から」始められる予防
「まだ大丈夫」と思っている今だからこそ、始め時。
特別なことをする必要はありません。
むしろ、「楽しくて、続けられること」こそが、いちばんの予防です。
近所の友人と散歩してみる。
週末の食事に、旬の野菜を取り入れてみる。
手帳の片隅に、ひと言日記をつけてみる。
そんな小さな習慣が、未来の自分を守ってくれます。
まとめ.自分を守ることは、家族を守ること
誰もが、できれば子どもに迷惑をかけたくないと思っています。
介護される前に、自分を守る備えをすることは、
大切な人たちを守ることにもつながります。
予防は、“誰かのため”であると同時に、“自分が人生を楽しむため”のもの。
「できることを、できる今から」
小さな一歩を、一緒に始めていきましょう🌿
日常から離れて、心と体をととのえる。
やすらぎの里の詳しい資料は、
こちらでダウンロードできます ↓



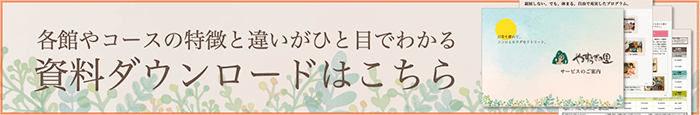













最近のコメント