
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
2本のにんじんがあるとして、農薬たっぷりの慣行農業よりも、愛情たっぷりの有機無農薬の方が、力がみなぎるだろうか。
農法であれ調理法であれ、いずれにしろ、優劣を判断したいという前提がある。
一方で、2本のにんじんは、ともに同じ生命であるという見方もある。
出自、境遇は異なっても、生き抜いてきた生命であることに変わりはない。
そこに優劣はつけられない。
自分の食べ方を顧みるに、「圧倒的に感謝が足りない」と痛感する。
「圧倒的」なのである。
頭の知識だけで善悪、優劣を判断し、観念だけで責め裁いている自分を発見した。
敬愛する二人のこんなエピソードがある。
『このあいだも鯉の活造りを食べましてね、食べてる間もピクピク動いてますよ、「殺生やなあ」と食べてる人が言った。それで私は言ったんです。「あなた、殺生という言葉をつかったら、この鯉が泣くよ。この鯉を往生させるんですよ。往生ということは、この鯉の命が私に生きて、私のなかで新しい生命を保っているんだ。私のなかで、もっと大きな働きをするためにこの鯉は死んでくれたのだ。そういう見方をしなきゃ、鯉に悪いよ」と。お互い殺して行かなきゃならんことがあるけど、すべて往生ですよ。そしてまた私も、どっかの生命のところへ行って、新しい大きな働きのために往生する、と。これが生命の連帯感でしょうね。』
増永静人先生の鯉の活け造りの話。
『私も少量ですが、肉を食べますよ。食べる前にちゃんとお祈りするから光が入ってゆく。一頭の豚を食べるわけではないですよ。わずかな肉だけれども、食べた肉を通して、一頭の豚に光が伝わってゆくのです。光は波(波動、響き)ですから、同じ豚の肉を知らないで食べた人でも、私が少し食べたために、みな浄まるわけです。だから皆さんが、「みんなが平和でありますように」という気持ちで食べれば、食べたものが栄養になり、そしてそれにつながってゆくものが、すべて浄まってゆくのですよ。』
五井昌久先生の豚肉の話。
つくづく、「食べる」という行為は、人間を人間らしくするものだ、と思う。
たしかに、食物には人間の肉体にプラスに作用する要素と、マイナスに作用する要素があるだろう。
つまり、良い面に目を向ければ、食べるべきものとなり、悪い面に目を向ければ、避けるべきものとなる。
しかし、両面併せ持っているのが人間を含めたあらゆる事物の、ありのままの姿なのだろう。
であるならば、なおさら「清濁併せ呑む」器量と、不安を安心に変える「感謝と全托」が必要ではないか。
どうせ食べるなら、この口に入る縁というものを、徹底的に肯定し生かし切っていく。
死んだその生命は何も語らないかもしれないが、この生命は引き受けたぞと背負いこむことで、うすっぺらな感謝よりもずっと重厚な人生観を醸成するに違いない。
「今、ここ」で食事に向き合う心こそ、大切にしていきたいものだ。








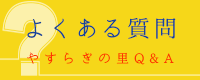


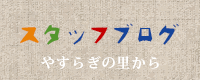







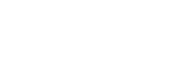

最近のコメント