以前「話せば長くなりますが」(https://y-sato.com/youjyoukan/yblog-001/227092016/)にも書いたが、
幼少時、反戦思想のコミュニティと接する縁があり、戦争の恐怖を植え付けられていたために、常に戦争におびえる子どもだった。
それは死の恐怖という根源的なものよりも表面的な恐怖であったように思うのだが。
大人になってから、出先で腹部の激痛に襲われたことがあった。
その場でうずくまり動けなくなった。
うなり声を漏らさずにはいられないくらい、数分おきに腸がよじれ握りつぶされるような痛みだった。
救急車が呼ばれ搬送された。
仰向けになれず腹をおさえるように硬直し痙攣していた。
容赦ない激痛に叫んでいたけれど、その合間は不思議と冷静で、お金の心配や、夜遅くまで付き合わせてしまっている娘たちの心配を頭の中でしていた。
搬送先の病院が決まるまで救急車は発車しない。
何か所も受け入れを拒否されているようで、もどかしい。
やっと決まった遠方の病院へ走り出すも、振動が痛みに拍車をかける。
着いたのだが、小規模のクリニック。
先に患者がいたようで、外来の待合室でストレッチャーごと待たされる。
衆人監視の中、叫ぶほかなかった。
抜け出してきた医師によって、その場で腹部の触診を受けたのもつかの間、いっぱいなので受け入れられないことが告げられる。
何のために待っていたのだろうか。
またもや救急車の中で搬送先を探す電話をしている。
痛みというのは主観的で、その切迫性をいくら訴えたところで伝わらないのも無理はない。
ましてや日々急病人に接しているプロである。
表向き同情はしても冷静である。
その間、数分おきの激痛は続くものの合間には、自分の思考や周囲の状況を冷ややかに見ることはできていた。
七転八倒していながらも、不思議と「死の恐怖」はなかった。
感じてもよさそうなのにと振り返ってみるのだが、拍子抜けするくらいなかった。
それは死に直結するものではないという体の確信があったからなのか、感傷的になる余裕すらなかったのか、はたまた修行の賜物なのか、生来の冷徹さゆえなのか、今でも判然としないのだが。
何度も繰り返される激痛に、声を絞り、全力でこらえるので、もはや疲労困憊であった。
次の病院で受け入れられた。
ここまでどれだけ時間がかかったのかわからない。
気の遠くなるほど、とても長く感じられた。
当直の医師は循環器科。
「わからない」とつぶやきながらレントゲンとCTを凝視して、一切こちらを見ず背中越しにすっとんきょうな問診をされる。
その間、鎮痛剤が点滴投与され次第に落ち着きをとりもどし、小康を得て帰宅を命じられる。
日付が変わる時間だった。
妻と娘はずっとそばにいて、ねぼけ眼で待っていてくれた。
ドラマのような生還の熱情もなく、楽しいはずの家族の休日に後味の悪さだけが残り帰路についた。
「医は仁術」
痛感した。
温かいまなざしと言葉、関心を向けて、共感してもらえるだけでどれだけ人は癒されることかと。
神さまは身をもって教えてくれた。
今度はもう少し手加減してください…








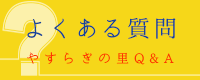


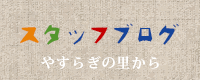







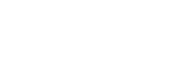

最近のコメント