クリックできる目次
〜迷いの中にこそ、やすらぎがある〜
先日、臨床心理士の物部先生を招いておこなわれた「瞑想リトリート」
今回のテーマは「ネガティブ・ケイパビリティ(Negative Capability)」
不確かな状況や迷いの中に「とどまる力」。
すぐに正解を出すことが求められる今の社会では、
「迷うこと」「決められないこと」が、まるで“悪いこと”のように感じられがちです。
やすらぎの里に訪れるゲストの中にも、
「決断できない自分が嫌なんです」
「もっとしっかりしなきゃと思うんです」
と話される方が少なくありません。
でも、本当にそうでしょうか?
もしかすると、その“迷い”の中にこそ、
あなたのやすらぎへの入り口があるのかもしれません。
1,「ネガティブ・ケイパビリティ」とは
この言葉の生みの親は、19世紀の詩人ジョン・キーツ。
彼は「人間には、不確実さや疑いの中に耐えてとどまる力が必要だ」と語りました。
白か黒かをすぐに決めるのではなく、
“分からないまま”を受け入れ、そこにとどまる。
それが「ネガティブ・ケイパビリティ(否定的能力)」です。
心理学者の河合隼雄先生は、この力を「葛藤保持力」と呼びました。
先生はこう言います。
「悩みや迷いがあるのが問題なのではなく、問題があるのにちゃんと悩んだり迷ったりしないことが問題なのだ。いろいろ葛藤を持ちながら、ぐっと耐えてそれを持ち続けられる。それが「おとな」ということ」。
つまり、“迷える自分”を否定するのではなく、
そのまま受け入れて、ともに生きる力こそが、成熟の証なのです。
2,「葛藤保持力」が私たちを支える
人生の後半になるほど、私たちは“正解がない問い”に出会います。
たとえば――
親の介護をどうするか、
長年連れ添ったパートナーとの関係をどう保つか、
仕事の終わり方をどう迎えるか、
体の衰えとどう向き合うか。
どれも、簡単に答えが出せるものではありません。
けれど、焦って白黒つけようとすると、心はどんどん疲れてしまいます。
大切なのは、
「迷いの中に立ち止まり、焦らず待つこと」。
時間をかけることで、
本当に自分にとって大切なものが、少しずつ浮かび上がってきます。
やすらぎの里で、ファスティング(断食)中に涙を流される方が多いのは、
体が静まり、心の奥にあった葛藤が、そっと顔を出すから。
それを無理に消そうとせず、
ただ“見つめる時間”を持つこと。
その静かな時間こそが、
人を強くし、優しくしていくのだと思います。
3,「答えを出さない時間」がもたらすリカバリー
不確かさを抱えることは、
同時に脳を休ませる時間でもあります。
いつも「どうするべきか」「何が正しいか」と考え続ける脳は、
思考モード(論理の脳)が働きすぎて、疲労しています。
だからこそ、意識的に“感じるモード”に切り替えることが大切です。
たとえば、
瞑想で呼吸に意識を向ける。
自然の中をゆっくり散歩する。
湯船に浸かって、ただ湯の感覚を味わう。
これらはすべて、「答えを出さない時間」。
その間に体はゆるみ、呼吸が深まり、
張りつめていた心が静かにほどけていきます。
「すぐに動く」よりも、「いったん立ち止まる」。
その勇気こそが、今の時代に必要なリカバリー(回復)なのです。
4,「やすらぎの里」で感じる“答えのない時間”
「何もしない時間が、いちばん贅沢でした。」
これは、やすらぎの里でよく聞く言葉です。
食を断ち、自然の中で過ごすうちに、
焦りや不安がすこしずつほどけていく。
「何もしていないのに、心が整っていく」――
そんな不思議な時間が流れます。
“今ここ”に意識を向けると、
頭の中の「過去」や「未来」の雑音が、静まっていく。
そして、迷いながらでも、
「これが今の自分でいい」と思えるようになる。
その瞬間こそが、
“葛藤保持力”が育まれる時間なのです。
【 まとめ 】
人生には、すぐに答えが出ないことの方が多い。
だからこそ、迷いや揺らぎを「悪いもの」とせず、
そのまま抱えていく力が、私たちを支えてくれます。
「何も決まらない時間」こそが、
葛藤を熟成させ、人生を深めていく。
やすらぎの里は、
“ゆるむ・休む・気づく”という3つの循環で、
人が本来の自分に立ち戻るお手伝いをしています。
迷いも葛藤も、あなたの一部。
そのすべてを受け入れられる場所でありたいと願っています✨
👉【休んでも抜けない疲れ】「気づく→整える」体系的リカバリー
資料ダウンロード・空室確認
やすらぎの里3館の詳細やプログラム内容は、資料ダウンロードか空室確認・予約ページからどうぞ。


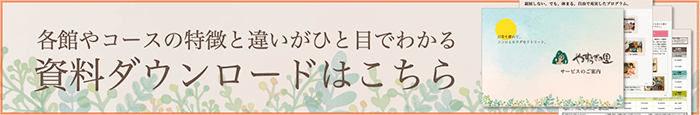













最近のコメント