クリックできる目次
〜🌿手放すことで、ととのう〜
私たちは、いつの間にか「がんばること」が当たり前になっています。
家族のため、仕事のため、誰かの期待に応えるために、
少し無理をしてでも前に進もうとする。
けれど、ふと立ち止まったとき、
「こんなにがんばっているのに、なぜ苦しいんだろう」
そう感じたことはありませんか?
そんなときに出会いたい一冊が、
五木寛之さんの『あきらめる力』(PHP新書)です。
「あきらめる」は“投げ出す”ことではない
五木さんが語る「あきらめる」は、
一般的な“もうダメだ”という意味ではありません。
もともと「あきらめる」という言葉は、
「明らめる(あきらめる)」――つまり“明らかに見極める”こと。
どうにもならないことを受け入れ、
自分の力では変えられない現実を静かに見つめること。
それこそが、本当の意味での「あきらめる力」です。
私たちは、努力すればなんでも変えられると思いがちですが、
実際には、思い通りにならないことのほうが多いもの。
その現実を“負け”と捉えるのではなく、
「見極めて手放す」ことで、初めて心が軽くなる――
そんな生き方を、著者は静かに勧めています。
「あきらめ下手」な現代人へ
五木さんは、「現代人はあきらめ下手だ」と言います。
努力・前向き・根性といった言葉が並ぶ社会では、
“あきらめること=悪いこと”と教えられてきました。
でも、どれだけ頑張っても叶わないこと、
努力ではどうにもならない現実は、誰にでもあります。
そんなとき、無理に頑張り続けるより、
「ここまでやったから、もういい」と区切りをつける勇気。
それは逃げることではなく、
“自分を守る知恵”なのだと、この本は教えてくれます。
あきらめると、心は自由になる
執着を手放したとき、人は不思議と自由になります。
「こうあるべき」「もっと頑張らなきゃ」という思いを降ろすと、
小さな幸せや安らぎが、ふっと見えてくる。
五木さんはこれを「人生の下山の思想」と呼びます。
若い頃のように上を目指すのではなく、
穏やかに“降りていく”生き方。
力を抜いて、静けさの中に身を置く。
それは、やすらぎの里で過ごす時間にも似ています。
断食で“食を断ち”、
温泉で“力を抜き”、
自然の中で“何もしない”。
その「手放す時間」が、心と体をととのえてくれるのです。
あきらめの先にある、希望
五木さんは言います。
「あきらめることは、希望を失うことではない。」
むしろ、あきらめたときに初めて、
現実の中にある“ささやかな幸せ”に気づけるのだと。
“希望は、あきらめの先にある”。
この逆説に、深いやすらぎがあります。
無理に前向きにならなくてもいい。
悲しみや迷いを抱えたままでも、
人は静かに生きていける。
あきらめる力とは、
がんばりすぎる自分をやさしく解放する力なのです。
🍃 おわりに
「手放す」「降りる」「委ねる」――
どれも、やすらぎの里で大切にしている言葉です。
断つことで、休める。
休むことで、気づける。
頑張ることを少し手放したとき、
“今ここ”にある小さな幸せが見えてきます。
もしかしたら、
それが本当の「ととのう」ということなのかもしれません。
👉【休んでも抜けない疲れ】「気づく→整える」体系的リカバリー
資料ダウンロード・空室確認
やすらぎの里3館の詳細やプログラム内容は、資料ダウンロードか空室確認・予約ページからどうぞ。

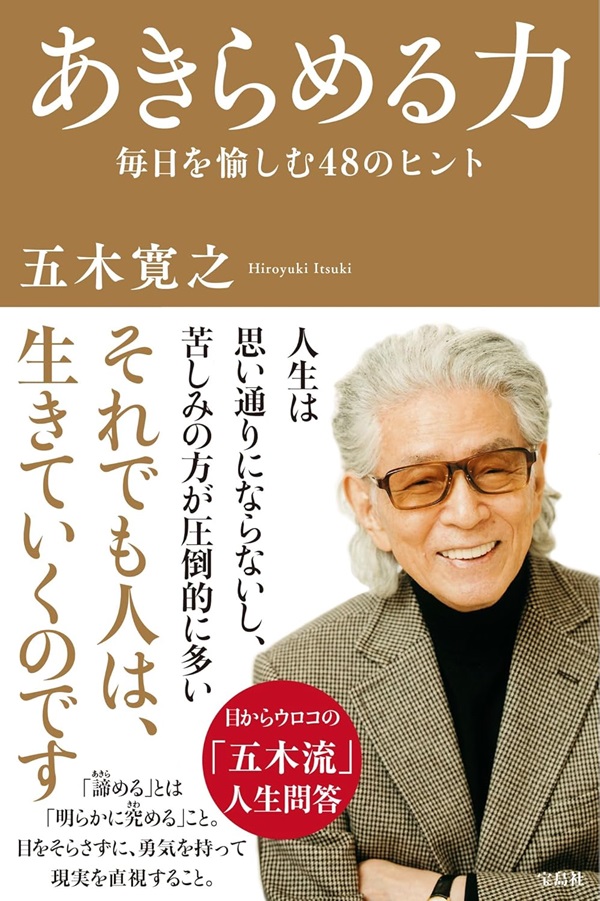
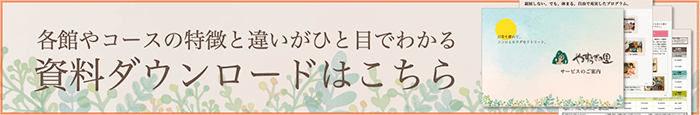












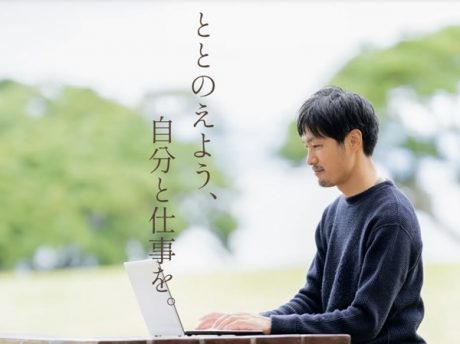
最近のコメント